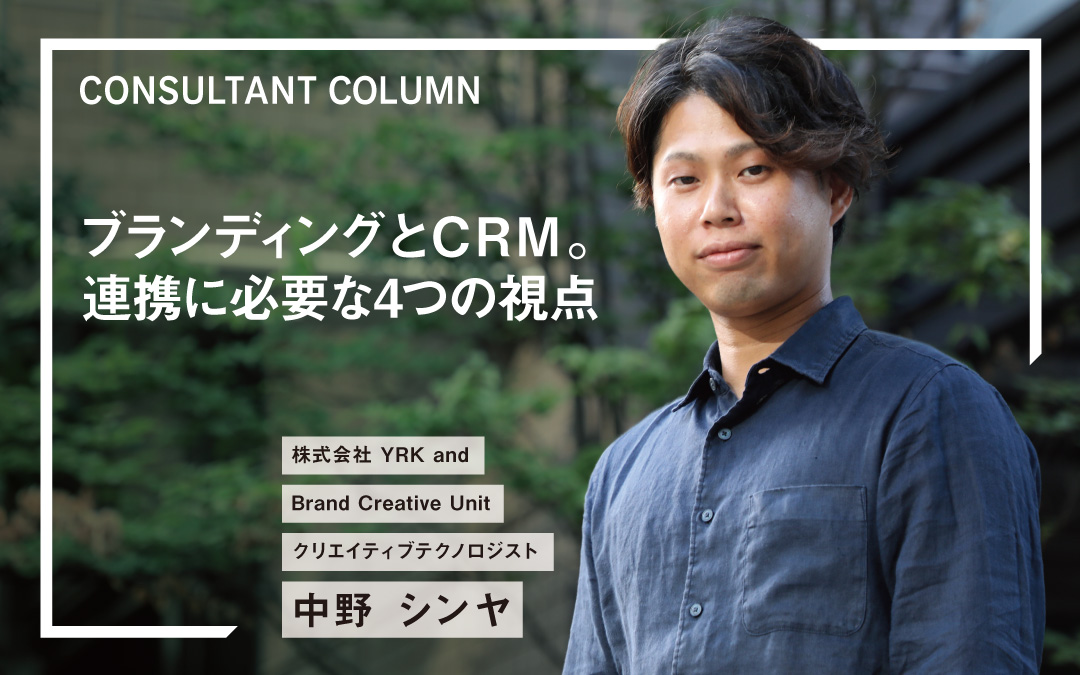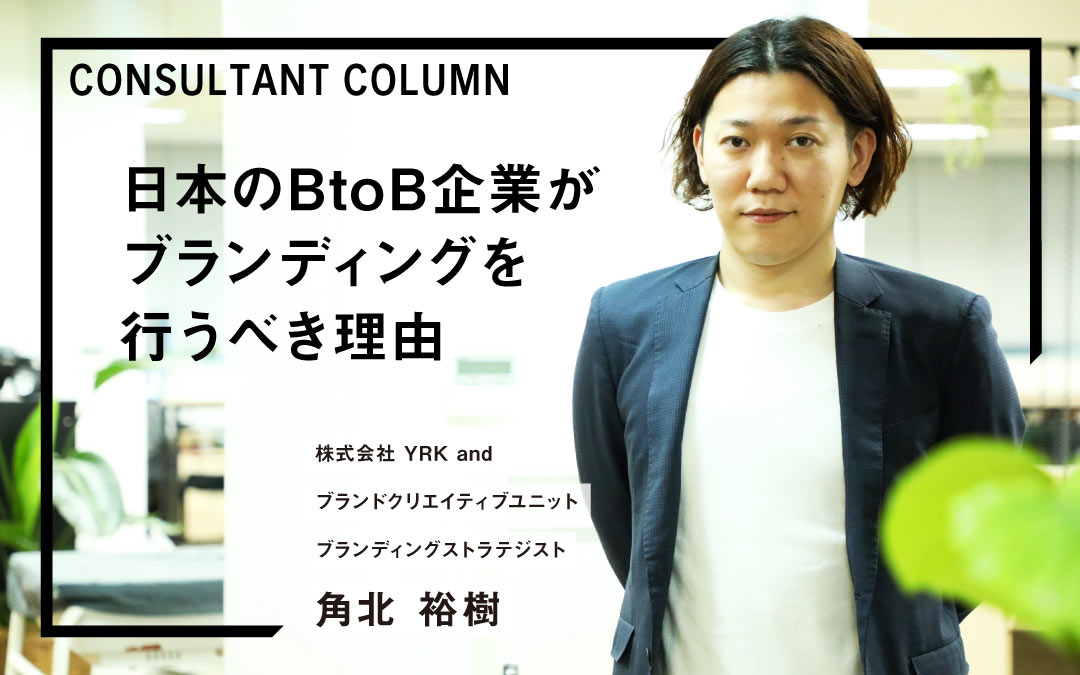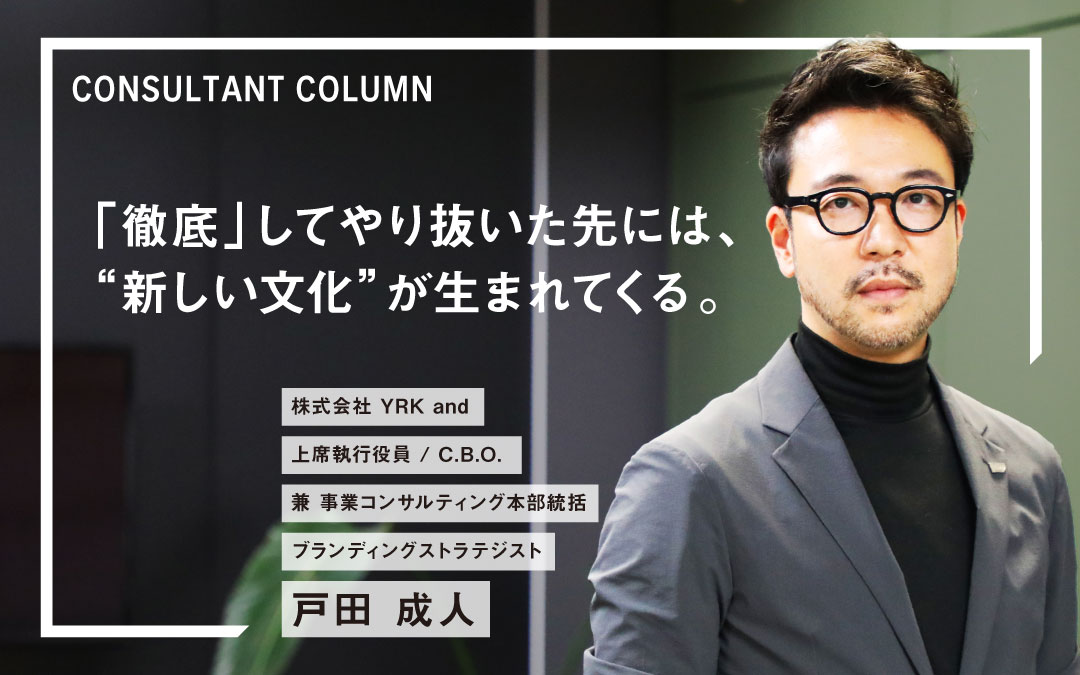COLUMN
コラム
当社コンサルタントが「ブランディング」や「事業変革」をテーマに、独自視点の論考・コラムを発信しています。
-

ブランディングとCRM。連携に必要な4つの視点
昨今、さまざまな企業で取り組みが進む“ブランディング”、そして“CRM(顧客関係管理)”。「まさに今真っ最中」「これから取り組む・検討中だ」といった企業様も多いのではないでしょうか?業務領域やチームの“分断を理由に、担当間の連携がなされていない”状況が存在します。連携する必要性と連携のポイントについて綴ります。
-

【BtoB企業ブランディング】なぜBtoB企業に「ブランディング」が必要なのか?
ブランドは大きく捉えると「識別記号」と「知覚価値」の掛け合わせで構成されています。「識別記号」とは、その商品や企業などブランドを識別する文字や形、色など生活者や顧客がブランドを識別する際の、記号的要素です。
-

廃業寸前の縫製工場を救った「笏の音」ブランド 3代目社長が語る、総理大臣に届くまでの軌跡。
株式会社笏本縫製は、岡山県津山市にある縫製会社です。今回のトップ対談では、廃業寸前という窮地から、「笏の音」ブランド成功に至るまでの成功の裏側を余すことなく語っていただきました。OEMの会社がいかにして自社ブランド立ち上げ、総理大臣に身につけてもらうネクタイブランドにまで成長した軌跡を動画コンテンツでお楽しみください。
-

ブランディングの強さと、組織の力は連動する。
ブランディングがいかに万能で、どれだけ広範囲に経営や事業戦略にも適応できるのか?また、逆にブランド戦略を適応しないことが、いかにリスクであるか?という側面から、商品やサービス以外のブランド戦略導入のメリットを語っていきたいと思います。
-

リブランディングによる、業績向上のための3領域。
「業績向上を目的にするなら、リブランディングに投資するのが早道だ」と、社内で論理的に説明ができたらどうでしょう?少しは話を聞いてもらえるような気がしませんか?。 今回は業績向上のための「リブランティング投資」を実現するための重点ポイントについて紐解いていきます。
-

「徹底」してやり抜いた先には、“新しい文化”が生まれてくる。
ある経営者様の言葉をヒントとしてコラムを綴ります。一流ブランドへと育った「スターバックス」の事業成長に日本上陸時から関わり、事業変革リーダーとして800店舗、2万人の組織にまで成長させ、その後「SABON」を日本で52店舗も展開した黒石和宏氏。「サービスやプロダクトを通じて生み出す、“新しい文化”」とは?
-

20年で65%もダウンした低迷市場に対し、 付加価値戦略でファン獲得に成功した「SWANS」のブランディングに迫る。
【&magazine09】今回は、山本光学株式会社 代表取締役社長の山本直之様との対談です。20年間で65%ダウンと低迷したウィンタースポーツ市場における歴史とファンを獲得したマーケティング施策、これからの未来に向けて取り組むサステナビリティビジネスについてお話しいただきました。
-

大阪・関西万博とリ・ブランディング
「大阪・関西万国博覧会」を事業成長にどう取り入れるべきか?を紐解いた、サステナブル経営の本質に迫るコンサルタントコラムです。2025大阪・関西万博のテーマは「SDGs」。本コラムでは関西に根付く「商人道」、特に近江商人の「三方良し」は、世界に類を見ない価値観でありSDGsに通ずる点が多く存在します。
-

温故創新の事業承継に必要な「ブランディング」とは?
我々は事業承継を単に、経営権・財務的資産・現状の競争力の源泉・無形の資産などの引き継ぎと考えず、企業トップが代わり若返る時こそ、バックキャスティングで将来を見据えた新しい企業のブランド価値を社内外のステークホルダーすべてに発信できる機会と捉えます。
-

ブランディングにも精通する3つの要素、ロゴス、エトス、パトスとは?
人を説得して動かすために必要だとされているアリストテレスが述べた「論理(ロゴス)」「信頼(エトス)」「情熱(パトス)」 という3つの要素には、現代のブランディングにも精通している共通項があります。普遍的な哲学をブランディングという視点で考察しています。
-

「ブランドストーリー」とは? ブランディングにおいて、なぜ「ストーリー」は大切なのか?
「ブランドストーリー」とは? 企業がビジネス活動をするなかで、広告、PRなどはもちろん、ビジネスパーソンが日常で行うプレゼンテーションにも「ストーリーテリング」は重要となってきます。実際の事例を交えながら企業のブランドストーリーの作り方とポイントについて紐解いてまいります。記事の詳細はこちらから
-

ブランド力はサステナブルで強くなる 。
『「らしさ」探しと「好き」のメカニズム』ESGやSDGsを含めたサステナブルな取り組みをうちの会社で考えるために、他社の情報を収集しているうちに、「うちは他社に負けている」「うちは遅れている」「経営陣も社員も意識や理解が足りない」という考えに陥りがちですが、それは違います。